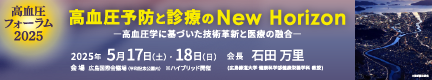公募シンポジウムのご案内
以下、9個のシンポジウムを公募いたします。(公募シンポジウム5は公募無し)
「テーマ」と「公募趣旨」は以下の通りでございます。
皆様のご応募、お待ちいたしております。
演題募集期間
2025年4月2日(水)正午 ~ 6月17日(火)正午まで
演題応募を締め切りました。
- 一般演題と指定演題は7月1日(火)正午まで登録可能となります。
- 公募シンポジウムのみ予定通りで締め切らせていただきます。ご了承ください。
公募シンポジウム1
テーマ
高血圧の外来診療・患者指導に直接役立つ疫学研究の最新知見
公募趣旨
外来高血圧診療における患者指導ですぐに使える様々な知見が、一般住民・健常労働者等を対象とした疫学研究や患者集団を対象とした臨床疫学研究から生み出されている。例えば、家庭血圧測定のタイミング・変動性、あるいは生活習慣改善(減塩指導、飲酒指導など)・ストレスコーピング、また近年ではアプリの利用などのデジタルデバイスに関する知見も蓄積されつつある。
我が国の高血圧管理の主たる場は外来であるが、未だ高血圧管理率は不良である。漫然とした薬物治療のみでは臨床イナーシャの打開は困難であり、疫学研究を含む様々な視点からの対策が必要である。
本セッションでは,外来診療・患者指導に直接役立つ疫学研究からの知見について、幅広い視点からの応募を期待している。
公募シンポジウム2
テーマ
知っておきたい最近話題の高血圧成因
公募趣旨
本態性高血圧の成因は、未だ完全には解明されていない。これまでの研究により、遺伝的素因や交感神経系の亢進、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系の亢進、血管内皮異常、食塩感受性の増大、インスリン抵抗性・代謝異常、環境要因、DNAメチル化などのエピジェネティック変化といった多因子要因が複合的に関与すると考えられている。加えて、最近では腸内細菌叢や免疫系の関与も報告されており、環境要因と生活習慣が深く関わることが分かってきた。さらに、心臓や腎臓、肝臓、脾臓、脂肪組織が内分泌臓器として様々なホルモン様分子を分泌し、高血圧形成に関わることも注目されている。本セッションでは、基礎から臨床まで高血圧の成因に関わる新たな視点をもたらす幅広い知見を共有したく、演題を募集する。
公募シンポジウム3
テーマ
収縮期血圧、拡張期血圧、脈圧を考慮した高血圧の診断と評価
公募趣旨
動脈圧波の周期において約70%が拡張期であることから、1980年代までは高血圧が心血管系に及ぼす影響の指標として拡張期血圧がより重視され、大規模臨床試験における血圧の評価も拡張期血圧に基づいて行われる場合が多かった。しかし、その後、疫学的な研究から脳心血管イベントのリスクには収縮期血圧の方がより密接に関係することが明らかになり、大規模臨床試験によるエビデンスも収縮期血圧を指標として構築されることが多くなった。また、脈圧の開大は動脈壁弾性の低下を反映し脳心血管病のリスクに関係すると考えられるが、逆に脈圧が小さくなる孤立性拡張期高血圧にどのように対応するべきであるかは問題である。本シンポジウムでは、臨床においてこのような血圧の指標を正確に測定するとともに、その生理学的、疫学的な意義を確認し、脳心血管病予防の観点からそれらをどのように評価して介入するかを考えたい。
公募シンポジウム4
テーマ
減塩とカリウム摂取の増加:実践と有用性
公募趣旨
減塩に加えてカリウム摂取が増えると高血圧の予防、降圧ひいては心血管病発症リスクを減らすとされている。このためJSH2025においても食塩制限<6g/日未満とともにカリウム摂取増(男性3000㎎、女性2600㎎/日以上)によりナトリウム/カリウム比を下げることを生活習慣修正項目のポイントに記した。しかしながら高血圧患者においても食塩摂取6g未満を達成できている者は少なく、食塩とカリウム摂取量は正相関する。このため、減塩しつつカリウム摂取量を増やすことは実践が難しいことが予想される。このような背景の中で減塩とカリウム摂取増の実践とその有用性についての研究報告の蓄積は国民や高血圧患者への指導に役立ち、それに伴う血圧低下や血圧管理につながりうるため、本セッションを企画した。当日は減塩・カリウム摂取増・ナトリウム/カリウム比を中心とした実践とその有用性について、今後の展開も含め議論していきたい。
公募シンポジウム5
テーマ
高血圧性腎硬化症の治療戦略
公募趣旨
公募無し
公募シンポジウム6
テーマ
脳小血管病と認知機能障害
公募趣旨
高血圧は脳小血管病の主要なリスクであり、細動脈硬化が進めば、脳血流低下、血液脳関門の破綻を介して、大脳白質病変、微小出血、ラクナ梗塞、血管周囲腔拡張などが生じる。こうした変化は脳MRI画像で評価が可能であり、評価スコアも考案されている。こうした虚血・出血性変化により、情報伝達を担う神経ネットワークが障害され、記憶や判断力の低下を含む認知機能障害が進行する。特に血管性認知症のリスクが高まり、アルツハイマー病の進行にも関与する可能性が指摘されている。早期アルツハイマー病に対する抗アミロイドβ抗体薬投与時に一定頻度で観察されるアミロイド関連異常(ARIA)の発生は、脳小血管病の一つである脳アミロイド血管症を背景とし、高血圧症と正相関、降圧薬使用と負相関することが知られている。抗アミロイドβ抗体薬が登場し、認知症診療が新時代に突入した今、本シンポジウムは、認知症予防の観点から高血圧管理と脳小血管病について論ずる機会としたい。
公募シンポジウム7
テーマ
小児から高齢者までの高血圧を考えよう
公募趣旨
高血圧および血圧管理は、小児期から超高齢期までのライフコースにおいて重要なテーマです。小児期には、胎児期環境の影響、小児肥満や生活習慣との関連、二次性高血圧の鑑別、さらには将来的な本態性高血圧への移行などが課題となります。妊娠期には、妊婦の高年齢化に伴い、妊娠と関連した高血圧への理解と適切な管理が不可欠です。近年、高血圧の予防と治療における性差も重要視されています。高齢期では、臓器障害や生理機能の個人差が大きくなり、降圧治療の個別化が重要となります。人生100年時代を迎え、脳血管病最大リスク因子である高血圧への真の対策として、ライフコースでの健康リスクの累積を意識した高血圧への理解が求められているのではないでしょうか。本シンポジウムでは、年齢横断的な視点に加え、ライフコースを通じた高血圧診療および予防の課題と、その解決に向けた実践的・学術的展望を共有することを目的に、広く演題を募集します。
公募シンポジウム8
テーマ
原発性アルドステロン症の診断と治療Update
公募趣旨
原発性アルドステロン症(PA)は全高血圧患者の5~10%あるいはそれ以上と二次性高血圧のなかで最も有病率が高く、臓器障害も多いため、的確な診断および早期治療が極めて大切である。診断にはスクリーニングから機能確認検査、病型・局在診断への流れが重要であるが、これらそれぞれの検査における課題も少なくない。治療に関しては、複数のMR拮抗薬の登場以来、薬物療法の有用性が示されつつあるが、手術適応の有無、副腎摘出術と薬物療法との差異についてさらに検討が進められている。一方で近年、PAの病因に関する研究や、インターベンションを含めた新規治療法の開発も進められている。本シンポジウムでは、最新の診断と治療を含めた今後のPA診療の展開について議論することを目的とする。
公募シンポジウム9
テーマ
CKM症候群における降圧治療戦略
公募趣旨
CKD症候群(cardiovascular-kidney-metabolic syndrome)は心血管疾患(CVD)・腎臓病・2型糖尿病・肥満の強い関連性を特定し、CVDリスク、予防・管理に対する戦略を再考するために提唱された概念である。さらにCKM症候群は「ステージ0(危険因子がなく、完全に予防が焦点)」から「ステージ4」(心血管疾患を伴う、腎不全が含まれる場合もある)まで5段階で管理されており、多病態(横)と進行度(縦)が複雑に絡み合った病態概念となっている。高血圧はこれらのすべての段階で重要な因子となっており、降圧療法の是非がCKM症候群攻略の大きなカギを握っているとも言える。本シンポジウムではCKD症候群の縦と横を意識した降圧療法戦略を専門家から総括していただくとともに、新しい戦略、エビデンスや将来的な展望などをディスカッションしていきたい。
公募シンポジウム10
テーマ
アプリ・ウエラブル・オンライン 高血圧デジタル診療の現状と未来
(生成AIやEDCデータの臨床・研究への応用も含めて)
公募趣旨
高血圧診療は、様々なデジタルデバイスの進化と社会実装に伴い大きな転換点を迎えています。治療アプリを活用した高血圧デジタル療法、ウェアラブルデバイスによる24時間血圧モニタリング、高血圧オンライン診療による通院負担の軽減、さらには生成AIを含む機械学習による膨大な医療データの解析は、高血圧個別化医療の実現に向けて新たな可能性をもたらしています。本シンポジウムでは、高血圧デジタル診療の最前線で活躍する専門家が集結し、臨床現場での活用事例と課題、そして未来への展望を共有します。またEDCデータの臨床研究への応用や、AIによる診断支援システムの開発など、明日の高血圧デジタル診療を形作る革新的な取り組みについて議論します。デジタルが牽引する高血圧個別化医療の新時代を共に切り拓きましょう。